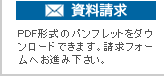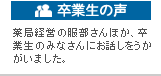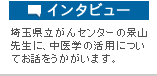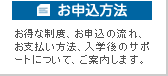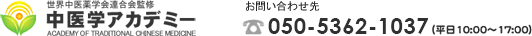インタビュー
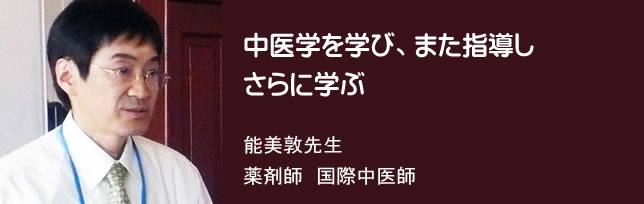
中医学との出会い
| 薬科大学を卒業し、郷里に戻って家業の薬屋を継いだ頃、わけもわからずにカネボウ(現クラシエ)の漢方薬をお店に並べていました。そこに訪ねてきた先輩に「お前、漢方の事は分っているのか?」と問われ、そういえば大学でもちゃんと学んだ覚えがないなと・・そこから勉強会に参加するようになりました。 運の良いことに、ちょうど「全国に漢方指導ができる人材を育てる」という2年がかりのプロジェクトが発足し、私も候補者として選ばれました。 勉強は簡単なものではありませんでしたし、卒業試験も、過去問を暗記すれば解けるようなものではなくて、漢方薬に対する的確な理解が試される内容でしたが、やりがいはありました。 | 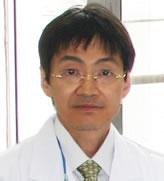 |
中医学を学ぶむずかしさ、楽しさ
それまでの、伝統的に日本で行われている漢方は、学べば学ぶほど疑問が増えていきました。たとえば虚証と実証はどこで線引きをすればよいのか?「経験を積めば分かるようになる」と言われましたが、それでは経験を積むまではどうするのか? ところが中医学では、学べば学ぶほど謎ときのような面白さがあって、おおいに手応えを感じたものです。
さらに、神様のような師匠との出会いも支えになりました。風邪で勉強会に参加できなかった私の妻を、一服の処方だけでその日のうちに治された先生もおりました。その先生は「本当に正しい処方なら一服で治せる」と常々言われていましたが、このような達人のわざを目の当たりにした感動もあって勉強にのめり込んでいったと思います。
どこまでも学び続ける事が大事
気が付けば、あれから25年以上が経ち、今では教える側として全国を回る立場になっていますが、師匠と尊敬する先輩たちの「もの凄さ」には、まだ到達できていないと思います。なにしろ、壁をびっしりと埋めた大量の専門書がほとんど漢書で、それを原文のまま参照していましたからね。私も、若い漢方医には中国語(漢文)くらい読めるようにしておこうよ、と言っています。
それから、どこまでも学び続ける事が大事。ただし点数や「お免状を取るため」の勉強にならない事が大切です。正しい処方なら一服で治せる・・我々は、「患者さんを治してナンボ」です。いくら免状を壁に飾っても、出した薬で患者さんが治らなければ無意味です。 西洋医学とは違う形で、2000年以上もかけて発展し、現在も多くの人を助けている中医学には、たしかに実効性があります。どこまでも学び続けるに値する、大きな価値があると思います。